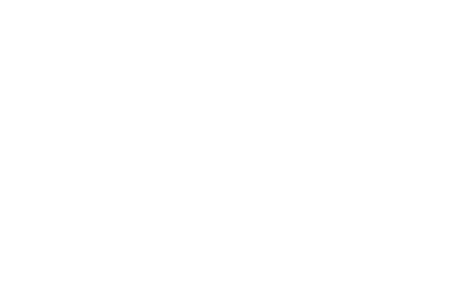墓じまいを行う手順
2023.03.20
これまでご先祖様を祀り、供養を続けてきたお墓の墓じまいを検討するご家庭が増えてきているのをご存じでしょうか。
墓じまいとは、亡くなった人の遺骨を移動させたり、墓石を撤去したりして、墓を閉じることを言います。
墓じまいを行う理由としては、葬儀や供養に対する考え方の変化、墓地の縮小などがありますが、核家族化や少子化によって、お墓を受け継ぐお子さんがいないことから、自分の代で墓じまいをするというケースがとても多いです。
そこで今回は、墓じまいを行う手順について紹介したいと思います。
まずは、お墓のある自治体や墓地管理者、墓石業者などに連絡をし、墓じまいに関する手続きを行います。手続き内容は、各自治体の規則によって異なりますが、遺骨の埋葬方法など、届け出などが必要な場合があります。
ひと通りの諸手続きを済ませたら、遺骨の移動を行います。遺骨は、火葬場や納骨堂などで適切に管理された上で、葬儀場での一時保管後、改葬先の墓地に移動されます。
遺骨が移動された後、墓地に残された墓石を撤去します。墓石を撤去する場合、専門業者に依頼することになるので、事前に相談・依頼を行うようにしましょう。
墓石が撤去された後は、墓地の整地も併せて依頼します。
墓じまいが完了したら、関係する自治体や墓地管理者に報告を行い終了となります。
今回紹介した墓じまいの手順は、ほんの一例なので、墓じまいを行う遺族や、地域、墓地の状況によって異なる場合があります。
墓じまいの参考という形で、ぜひご活用ください。